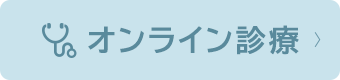皮膚科(一般・小児)について
 皮膚のトラブルや病気は、年齢や性別を問わず、どなたにも起こりうる身近なものです。特に下着や衣服で蒸れやすい部位は、汗や老廃物が溜まりやすく、炎症やかゆみなどの症状が出やすくなります。
皮膚のトラブルや病気は、年齢や性別を問わず、どなたにも起こりうる身近なものです。特に下着や衣服で蒸れやすい部位は、汗や老廃物が溜まりやすく、炎症やかゆみなどの症状が出やすくなります。
しかし、「見られたくない場所だから受診に抵抗がある」「放っておけば自然に治るだろう」といった理由から、診察を躊躇われる方も少なくありません。
当院では、丁寧な診察を心がけ、患者様1人ひとりのお気持ちに寄り添った治療をご提案しております。気になる症状がある場合は、「こんなことで受診してもいいのかな」と思わずに、どうぞお気軽にご相談ください。早期に解決できるようサポートいたします。
また、当院では子どもの皮膚疾患も専門にしております。小児アトピー性皮膚炎、円形脱毛症、おむつかぶれ、とびひ、みずいぼなど子どもに多い皮膚疾患はもちろんのこと、小児のアレルギー症状にも対応しております。子どもの皮膚に何か異常を感じた際は、是非当院にご相談ください。スタッフ一同、優しくお迎えいたします。
当院で対応している主な疾患
水いぼ
水いぼは、「伝染性軟属腫ウイルス」によって引き起こされるウイルス性の感染症です。
主に乳幼児から小児に多く見られ、特に夏場はプールなどを介して感染が広がりやすくなります。加えて、アトピー性皮膚炎や乾燥肌のあるお子様は、皮膚のバリア機能が低下しているため、感染しやすく、水いぼが多数できる傾向があります。
治療方法
治療の基本は、ピンセットで1つひとつ摘まんで取り除く「摘除法」です。処置に伴う痛みを軽減するために、事前に麻酔成分を含んだ「ペンレステープ」を貼ってから行うことがあります。ペンレステープを使用する場合は、施術までにお時間がかかりますので、早い時間帯の受診をお勧めいたします。
他の治療法として、当院では水いぼの外用クリーム「3A M-BF CREAM」の販売も行っております。銀イオンによる抗菌・抗炎症作用と保湿成分サクランが、水いぼの治癒を促します。1日2回、患部に塗布するだけで治療でき、痛みが少ないため特に小さなお子様に適しています。治療期間は通常2〜3か月で、赤みやかゆみなど軽い副作用が出ることがありますが、重篤な副作用は稀です。保険適応ではないので、自費購入となります。
また、ヨクイニンというハトムギを主成分とした薬を内服する方法があります。上記2つの治療法に組み合わせることで、治療期間を短くすることが出来ます。再発を繰り返す場合にお勧めしています。
ウイルス性いぼ
ウイルス性いぼ(尋常性疣贅)は、「ヒトパピローマウイルス(HPV)」の感染によって発症するウイルス性のいぼです。特にお子様の手や足の裏などにできやすいとされています。
ウイルスは100種類以上の型が存在し、健康な皮膚には感染しにくいものの、目に見えないほど小さな傷から侵入していぼを形成することがあります。
初期はいぼが小さく平らで目立たない場合もありますが、時間の経過とともに硬くなり、表面がザラついて盛り上がってくるのが特徴です。足の裏にできた場合は、体重による圧力で盛り上がらず、皮膚の中に食い込むような形になることがあり、歩行時に痛みを感じることもあります。
治療方法
治療は主に3つの方法があります。1つは液体窒素という-196℃の低温の液体によっていぼを凍結させて破壊する「凍結療法」です。1から2週に1回の頻度で通院する必要があります。痛み、水ぶくれ、色素沈着などの副作用が起こることがあります。
2つ目は、薬剤を塗布し、ウイルスを攻撃しいぼを小さくする外用療法です。SADBE、MCA、硝酸銀などが用いられます。SADBE(スクアレン酸ジブチルエステル)は人工的なアレルゲンで、皮膚に軽い炎症を起こすことで免疫反応を活性化し、ウイルスに感染した細胞を排除します。MCA(モノクロロ酢酸)は強い酸で、いぼを化学的に壊死させて除去します。硝酸銀はたんぱく質を凝固させ、いぼを破壊します。上記の方法はいずれも、1回で完治することは難しく、複数回にわたる治療が必要となるため、継続的な通院が前提となります。
3つ目は、いぼを手術で切除する方法です。メスで紡錘形に切り取って皮膚を縫合する方法と、高周波ラジオ波メス(サージトロン)を用いて切除する方法があります。1回の手術で劇的ないぼの縮小効果が期待できます。
帯状疱疹
帯状疱疹は、「水痘帯状疱疹ウイルス」への感染によって引き起こされるウイルス性の感染症です。このウイルスに初めて感染すると水ぼうそう(水痘)を発症し、症状が治まった後もウイルスは体内から完全には排除されず、神経節に潜伏したまま残り続けます。
その後、加齢やストレス、過労などで免疫力が低下すると、潜伏していたウイルスが再活性化し、帯状疱疹として発症することがあります。
治療方法
治療の中心は、抗ウイルス薬(主に内服薬)による薬物療法です。
帯状疱疹は「帯状疱疹後神経痛」と呼ばれる後遺症が残ることがあり、痛みが長期間続くケースもあります。まずは鎮痛薬を用いて症状を緩和しますが、難治性の場合にはペインクリニックでの専門的な治療が必要となることもあります。当院では毎週日曜日に痛み外来を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
また、高齢の方や基礎疾患をお持ちの方、重症化している方に対しては、入院加療が必要となることがあります。その際は、大学病院やかかりつけの医療機関へご紹介させて頂きます。
ニキビ
 ニキビは、皮脂(皮膚の脂分)が過剰に分泌されることによって毛穴が詰まり、炎症が起こることで生じる皮膚トラブルです。
ニキビは、皮脂(皮膚の脂分)が過剰に分泌されることによって毛穴が詰まり、炎症が起こることで生じる皮膚トラブルです。
思春期のホルモンバランスの変化によるものだけでなく、ストレスや過労、睡眠不足、生活リズムの乱れ、誤ったスキンケアなども悪化の原因とされています。
治療方法
治療の中心は、外用薬を用いた薬物療法です。ニキビの状態や重症度、原因に応じて、抗菌薬や漢方薬、必要に応じてビタミン剤などの内服薬を組み合わせた治療を行います。膿を持ったニキビや詰まりが強い場合には、毛穴の内容物を取り除く「面皰圧出(めんぽうあっしゅつ)」という処置を行うこともあります。
乾癬
乾癬は、境界のはっきりとした赤い発疹に、銀白色の鱗屑(りんせつ)を伴う慢性の皮膚疾患です。発症は青年期から中年期にかけて多く見られ、症状が落ち着く「寛解期」と再び悪化する「再発期」を繰り返すのが特徴です。
症状は皮膚だけでなく、爪の変形や関節炎を伴うこともあり、これらが見られる場合は難治性となることも多く、必要に応じて専門医療機関をご紹介しています。
原因については明確には解明されていませんが、遺伝的要因のほか、不規則な生活習慣や食事、肥満、ストレス、特定の薬剤や感染症などが発症に関与している可能性があると言われています。
治療方法
当院では、ステロイド外用薬やビタミンD3外用剤を用いた外用療法を中心に、症状や状態に応じて内服薬による治療も行っております。
また、当院ではエキシマによる光線療法にも対応しております。光線療法は、紫外線(主にUVB)を皮膚に照射して炎症を抑え、症状の改善を図ります。皮膚のターンオーバーを正常化させ、赤みやかさつき、かゆみを軽減します。比較的安全で痛みが少なく、長期管理に適した治療法です。
アトピー性皮膚炎
皮膚は本来、外部からの刺激や異物の侵入を防ぐ「バリア機能」を持っています。アトピー性皮膚炎は、その機能が低下することで、アレルギー反応や刺激に過敏に反応し、慢性的に炎症やかゆみが繰り返し生じる病気です。
症状は「寛解」と「再発」を繰り返すことが特徴で、特に汗をかきやすい夏や、乾燥しやすい冬には悪化しやすい傾向があります。
治療方法
治療は、外用薬(ステロイド薬、タクロリムス軟膏、デルゴシチニブ軟膏など)を中心に、抗ヒスタミン薬による内服療法や注射薬を組み合わせて行います。当院では、生物学的製剤であるデュピクセント(デュピルマブ)を用いた治療も行っています。
エキシマによる光線療法にも対応をしており、紫外線を皮膚に照射することで、炎症やかゆみを和らげます。痛みはほとんどなく、週1〜2回の通院で徐々に効果が現れる、安全性の高い治療法です。
また、適切な保湿(スキンケア)の継続や、悪化要因の除去に努め、症状が起こりにくい環境を整えることも大切です。
ヘルペス
ヘルペスは、単純ヘルペスウイルスへの感染によって起こります。唇や口の周りに、チクチク・ピリピリとした痛みを伴う水ぶくれ(水疱)が現れるのが特徴です。
症状が治まってもウイルスは体内に潜伏しており、風邪をひいた時や疲労が溜まった時、免疫力が低下したタイミングで再発することがあります。
また、水疱が出ている期間は感染力が強いため、タオルの共用やキスなどで周囲に感染を広げてしまう可能性があります。十分な注意が必要です。
治療方法
治療は、抗ヘルペスウイルス薬の内服薬や外用薬が中心となります。発症から早期に治療を開始することが重要ですので、症状が出た際はお早めにご相談ください。
乳児湿疹
乳児湿疹は、新生児から乳児期にかけてよく見られる皮膚トラブルで、顔や頭部、首などに発疹が出るのが特徴です。
原因としては、皮脂の過剰分泌、乾燥、汗による皮脂減少などが挙げられます。症状は赤みのあるブツブツ、黄色いかさぶた、フケのような皮膚の剥がれ、膿を伴うものなど様々です。
治療方法
肌を清潔に保ち、保湿を行うなど、日常的なスキンケアが基本です。それでも症状の改善に乏しい場合は、ステロイド外用薬などを用いて症状を抑えます。
とびひ(伝染性膿痂疹)
とびひは、黄色ブドウ球菌やA群β溶血性連鎖球菌の感染によって発症する皮膚の病気です。水ぶくれ(水疱)、かさぶた、膿を伴う発疹など、様々な症状が現れます。
擦り傷や虫刺され、汗疹、湿疹などを掻き壊した傷口から菌が侵入し、赤みや腫れを伴いながらジクジクした水疱を作ります。この発疹がまるで「火が飛ぶように」広がることから「とびひ」と呼ばれています。
夏場は汗をかきやすく皮膚の露出も多いため、乳幼児を中心に流行しやすいですが、年齢や季節に関わらず発症することもあります。
治療方法
治療は、抗菌薬の内服と外用を組み合わせて行います。かゆみが強い場合には、抗ヒスタミン薬を併用して症状を和らげます。
手湿疹
手湿疹は、水や洗剤によって皮膚の皮脂や水分が奪われることや、アレルギー物質・化学物質への接触、物理的な摩擦などが原因で起こる皮膚炎です。
乾燥によるカサカサ、赤み、水ぶくれ(小さな水疱)、ジクジクした症状が出ることがあります。水仕事をする主婦に多く見られることから「主婦湿疹」とも呼ばれていますが、美容師や調理師など、手を酷使する職業の方にもよく発症します。
治療方法
皮膚が乾燥している場合は保湿剤を使用し、かゆみや痛みを伴う場合はステロイド外用薬を用いて治療を行います。
また、当院ではエキシマによる光線療法にも対応しております。紫外線を患部に照射し、炎症やかゆみを抑える治療法です。皮膚の免疫反応を調整して症状の軽快を促します。痛みはほとんどなく、副作用も少ないため、安心して受けていただくことのできる治療です。
蕁麻疹
蕁麻疹は、皮膚が突然盛り上がり、強いかゆみを伴う疾患です。限られた部位に出る場合もあれば、全身に広がることもあります。
原因は様々で、日光や物理的刺激が関与することもありますが、多くは明確に特定できません。症状は数時間から数日で消えることが多いものの、出る部位が移動しながら連日続くこともあります。ストレスや睡眠不足が誘因となるケースも知られています。
治療方法
治療は、抗アレルギー薬の内服が基本となります。
症状が慢性的に続く場合には、定期的な通院をお願いしております。症状の経過を確認しながら、内服薬の種類や量を調整し、状態に応じた最適な治療を進めていきます。
多汗症・ワキガ
多汗症は、頭部・顔・手足・脇などに過剰な発汗が見られる疾患で、日常生活に支障をきたすこともあります。「文字を書くと紙が濡れてしまう」「足の汗が強く、臭いが気になる」「冬でも脇汗で衣服に汗ジミができる」といったお悩みを抱える方も少なくありません。
当院では、症状の部位や程度、患者様のお困りに合わせた最適な治療法をご提案いたします。
治療方法
治療方法には、外用薬(抗コリン薬)とボトックス注射があります。外用薬は汗腺の働きを抑える塗り薬で、特に脇汗や手汗に対しては保険適用となりますが、かぶれなどの副作用が出ることがあり、また閉塞性緑内障や前立腺肥大などの持病がある方には使用できません。一方、ボトックス注射は汗を出す神経の働きを一時的に抑えることで発汗を軽減する治療で、特にワキや手のひら・足のうらなど多汗が気になる部位に有効です。効果は注射後数日から2週間ほどで現れ、約4〜6か月持続し、重度の腋窩多汗症の場合は保険適用となります。
円形脱毛症
円形脱毛症は、突然、円形に髪の毛が抜け落ちる脱毛症で、年齢や性別に関係なく誰にでも起こり得ます。症状は頭部に限らず、眉毛・まつ毛などの体毛にまで及ぶケースもあります。かゆみや痛みを伴うことはほとんどありません。
自己免疫疾患を背景に発症するケースもあるため、血液検査での評価が必要になることもあります。脱毛範囲が狭く、症状が軽い場合には自然に改善することも多く、気づかないうちに治っているケースも見られます。一方で、脱毛範囲が広がっている・長期間治らない・急激に進行しているといった場合には、お早めにご相談ください。
治療方法
円形脱毛症にはさまざまな治療法があり、当院では経験豊富な皮膚科専門医が患者様の状態やお悩みに応じて最適な治療をご提案しております。ステロイド・ミノキシジル外用薬は頭皮に直接作用し、炎症を抑えながら発毛を促します。ステロイド局所注射は脱毛部位に直接薬を注入することで免疫機能を抑制し、発毛を促す方法で、限局した症状に有効です。ステロイド内服薬は免疫反応を抑えて脱毛の進行を防ぐ治療です。冷却療法は液体窒素で皮膚を刺激し、血流を改善するとともに免疫細胞の働きを抑えて発毛を助けます。光線療法は脱毛箇所に紫外線を照射し、免疫のバランスを整えて炎症を抑える治療法で、当院ではエキシマによる光線療法に対応しております。
白癬(水虫)
白癬とは、「白癬菌(皮膚糸状菌)」というカビ(真菌)の一種が皮膚に感染することで生じる皮膚の病気です。感染した部位によって呼び名が異なり、
- 足:水虫(足白癬)
- 頭皮:しらくも(頭部白癬)
- 体:ぜにたむし(体部白癬)
- 股部:いんきんたむし(股部白癬)
と呼ばれていますが、これらはいずれも「白癬」に分類される疾患です。
白癬の中でも特に多いのが足白癬で、白癬の患者様の半数以上が足に症状を持っています。
足白癬の主な症状には、「足の指の間がジュクジュクする」「皮がめくれる」「白くふやけてかゆくなる」などがあり、蒸れやすい環境で悪化しやすくなります。
日本は高温多湿の気候により足白癬を発症しやすく、特に夏場には約4人に1人(25%)が足白癬を患っているとも言われています。
また、爪に白癬菌が感染して発症する「爪白癬」も多く、10人に1人がかかっているとの報告があります。
白癬の確定診断には、顕微鏡による菌の確認が必要です。ただし、市販の水虫薬などを事前に使用してしまうと、菌が見えにくくなり、検査結果に影響が出ることがあります。そのため、診察前の2週間以上は市販薬を使用せずにご来院ください。
治療方法
治療は主に抗真菌薬の外用または内服で行います。
外用薬のみで治療できるケースも多いですが、爪白癬の場合は内服薬が必要になることがあります。その場合は、服用前に採血を行い、安全性を確認いたします。
また、「症状が軽くなったから」と自己判断で治療を中断してしまうと、白癬菌が皮膚に残り再発する可能性があります。治療は医師の指示に従って最後まで継続しましょう。
胼胝 (たこ)
皮膚の一部に繰り返し刺激が加わることで、その部分の角質が厚く硬くなった状態です。
通常は痛みを伴いませんが、生活習慣や動作の癖によって足の裏以外にも発生することがあります。例えば、ペンだこ(指)、座りだこ(臀部)、赤ちゃんの吸いだこ(口周り)などがその例です。
治療方法
スピール膏などの角質軟化剤を使用し、硬くなった皮膚を柔らかくしてから除去していきます。必要に応じて、カミソリ・ハサミ・メスなどを用いて角質を削る処置を行います。
鶏眼(魚の目)
鶏眼は一般的に「魚の目」と呼ばれる皮膚疾患で、中心に芯のような硬い組織が見られるのが特徴です。
同じ部位に繰り返し圧力や摩擦がかかることで角質が厚くなり、芯が形成されます。この芯が神経を圧迫するため、歩行時に強い痛みを感じることがあります。
なお、お子様が「鶏眼」と診断された場合、実際はウイルス性のいぼ(尋常性疣贅)であることが多く、診断には慎重な判断が必要です。
治療方法
基本的には、角質を削る処置を行います。症状や状態によっては、魚の目のサイズに合ったスピール膏をご自宅で貼付して角質を柔らかくしてから、切除を行うこともあります。
また、歩き方の癖や合わない靴、圧迫部位などの原因を取り除かないと再発しやすいため、生活習慣の見直しも重要です。
白斑
白斑は、皮膚の色素が抜けて白くなる疾患で、先天性と後天性があります。後天性の白斑は「尋常性白斑(白なまず)」と呼ばれています。原因ははっきりと解明されていませんが、自己免疫の関与が指摘されており、自己免疫疾患や糖尿病などを合併しているケースもあります。
白斑は全身の様々な部位に現れ、感染することはありませんが、完治が難しい皮膚疾患とされています。尋常性白斑は以下のように分類されます。
- 全身に左右対称に発生するタイプ
- 口の周りや手足の指に限局して現れるタイプ
- 皮膚の神経に沿って片側にのみ現れるタイプ
治療方法
当院では、外用療法と光線療法の併用を行っております。外用療法は、ステロイド外用薬と活性型ビタミンD3外用薬、タクロリムス軟膏を併用し、症状の改善を目指した治療を行っております。また、光線療法は紫外線を白斑に照射することで、色素細胞の増殖や移動を促し、色素の回復を目指す治療法です。当院ではエキシマによる光線療法に対応しております。
掌蹠膿疱症
掌蹠膿疱症は、手のひらや足の裏に膿をもった小さな水ぶくれ(膿疱)ができる慢性の皮膚疾患です。原因は完全には解明されていませんが、自己免疫やストレス、喫煙、金属アレルギー、扁桃炎などが関係すると考えられています。症状は赤みやかゆみ、痛みを伴うことがあり、日常生活に支障をきたす場合もあります。
治療方法
治療は外用薬や内服薬などで炎症を抑え、症状を和らげることが中心です。重症例では生物学的製剤(抗TNF-α薬など)が用いられることもあります。
当院ではエキシマによる光線療法にも対応しており、紫外線を手のひらや足の裏に照射して炎症を抑え、症状を改善します。膿疱や赤み、かゆみを和らげる効果があり、外用薬と併用することでさらに改善が期待できます。
症状は慢性的に再発することが多いため、生活習慣の改善や定期的な受診が大切です。
赤ら顔・酒さ
赤ら顔とは、顔の皮膚の毛細血管が拡張して赤みが目立つ状態を指します。特に頬や鼻、額に出やすく、肌質や遺伝、加齢、ストレスなどが関係します。アルコールの摂取は血管を拡張させるため、赤ら顔を悪化させる原因のひとつです。飲酒後に顔が赤くなるのは、血流が増えることやアルコールの分解能力の違いによるもので、一時的に赤みが強くなることがあります。日常生活では、過度の飲酒を避けることや保湿・紫外線対策などのスキンケアが赤ら顔の予防・改善につながります。慢性的な赤みが続く場合は、当院までお気軽にご相談ください。
治療方法
治療には、外用療法、内服療法、そのほか自費治療を当院では行っております。外用療法は、ロゼックス®ゲル0.75%という、ニキビダニに強い殺菌作用を有する「メトロニダゾール」を主成分とした塗り薬を保険で処方しております。またロキシスロマイシン、塩酸ミノサイクリンなどの抗生物質を内服します。
酒さは、症状が良くなったり悪化したりを繰り返す傾向があり、保険の治療でコントロールが難しい場合は、自費の治療を組み合わせることもあります。当院では、DRX®AZAクリア®(アゼライン酸高濃度配合クリーム)を採用しております。アゼライン酸は皮脂分泌を抑え、抗菌、抗炎症作用があるため、酒さ以外に、にきびや毛穴の開きを改善する効果もあります。また、ニキビダニに効果のあるイベルメクチンクリームも採用しております。当院では他にも、酸を用いて古い角質を取り除き、肌のターンオーバーを整えるケミカルピーリングや微弱な電気パルスで美容成分を肌の奥まで浸透させ、炎症を抑えるエレクトロポレーションなどの赤み改善治療を行っております。さらに、水光注射によるボトックス治療は、酒さの赤みやほてり、毛穴の開きなどの改善に効果が期待できます。
また、にきび治療で用いられるイソトレチノインも皮脂分泌を抑え、炎症改善効果があり、顔の赤みを改善してくれるため、難治性の患者様に処方しております。
青あざ・茶あざ
太田母斑
顔の片側に青灰色の色素が出る先天性のあざで、メラノサイトの異常により起こります。生まれつきまたは思春期以降に目立つことがあります。
異所性蒙古斑
お尻や背中以外の場所に現れる青灰色のあざで、皮膚の深い層にメラニンが沈着してできる先天性の色素斑です。
ADM(後天性真皮メラノーシス)
顔や体に後天的に現れる青灰色のあざで、真皮にメラニンが沈着することで発生します。加齢や紫外線が関与することがあります。
扁平母斑
生まれつき見られる茶色の平らなあざで、境界がはっきりしていることが多く、悪性化の心配はほとんどありません。
外傷性色素沈着(外傷性刺青)
ケガややけど、刺青などの外的要因で皮膚に色素が沈着してできるあざです。色や範囲は原因によって異なります。
治療方法
当院ではQスイッチアレキサンドライトレーザー(ALEX-Q)を導入しております。特定の波長の光を皮膚に照射し、メラニン色素や異常な色素細胞を選択的に破壊するレーザー治療です。色素斑に効果があり、周囲の皮膚へのダメージを抑えながら治療できます。痛みやダウンタイムが少なく、複数回の照射で徐々に色素が薄くなることが期待できます。痛みが苦手な患者様には、施術前に麻酔クリームをお勧めしております。
上記に記載した疾患は保険適応となる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
麻疹、風疹、水痘
いずれもウイルスによって起こる感染症で、主に発熱や発疹を伴います。
麻疹は高熱や咳、鼻水、目の充血に加え、顔から全身に広がる赤い発疹が現れ、合併症として肺炎や中耳炎が起こることがあります。
風疹は軽い発熱や全身の赤い発疹、リンパ節の腫れが特徴で、妊婦が感染すると胎児に影響することがあります。
水痘(水ぼうそう)はかゆみを伴う水ぶくれ状の発疹が体全体に広がり、初めは発熱やだるさも見られます。
いずれも空気感染、飛沫感染、接触感染で広がるため、予防接種が重要です。
麻疹、風疹、水痘は、学校保健安全法に基づき、出席停止期間が設けられています。投稿再開にあたり、診断書や登校許可証が必要になる場合があります。事前に通学されている学校に確認して、必要があれば診察時にご相談下さい。
治療方法
風疹・麻疹
発熱やかゆみ、倦怠感に対して解熱鎮痛薬や抗ヒスタミン薬で症状を和らげます。水分補給や安静も重要です。重症例では入院加療が必要になることもあります。
水痘(水ぼうそう)
発疹やかゆみに対しては、外用抗ヒスタミン薬や保湿剤を用います。重症例や免疫力が低下している方には抗ウイルス薬(バラシクロビルなど)を内服することがあります。かき壊しによる二次感染を防ぐため、患部の清潔管理も重要です。