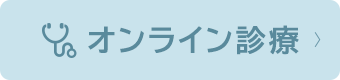アレルギー科では、アトピー性皮膚炎や気管支喘息、アレルギー性鼻炎、食物アレルギーといった各種アレルギー性疾患に対して、専門的な診断と適切な治療を行っています。
よくあるアレルギー疾患
アトピー性皮膚炎
 アトピー性皮膚炎は、強いかゆみを伴い、症状が繰り返し現れることが特徴の皮膚疾患です。湿疹が一度良くなっても再び悪化する場合には、生活習慣やお薬の使い方などを見直すことが大切です。特に外用薬は、種類だけでなく、塗布するタイミング・回数・量・お薬の強さなどによって効果に違いが出るため、正しい使い方が改善の鍵となります。
アトピー性皮膚炎は、強いかゆみを伴い、症状が繰り返し現れることが特徴の皮膚疾患です。湿疹が一度良くなっても再び悪化する場合には、生活習慣やお薬の使い方などを見直すことが大切です。特に外用薬は、種類だけでなく、塗布するタイミング・回数・量・お薬の強さなどによって効果に違いが出るため、正しい使い方が改善の鍵となります。
また、皮膚の状態を良好に保つためには、食事内容の調整や、汗・紫外線への対策、爪を清潔に保つなど、日常生活での細やかなケアが欠かせません。特に小さなお子様の場合には、ご家族による丁寧なサポートが大きな助けになります。アトピー性皮膚炎でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。皮膚科専門医が専門的な知識に基づき、最適な治療を提供します。
当院では、内服外用治療に加えて、生物学的製剤であるデュピクセント(デュピルマブ)を用いた治療も行っています。
蕁麻疹(じんましん)
 蕁麻疹は、皮膚に一時的な赤みやかゆみを伴う発疹が現れる疾患で、原因は多岐にわたります。アレルギー反応によって起こる場合もあれば、摩擦・発汗・寒冷刺激などの非アレルギー性の要因によって生じるケースもあります。
蕁麻疹は、皮膚に一時的な赤みやかゆみを伴う発疹が現れる疾患で、原因は多岐にわたります。アレルギー反応によって起こる場合もあれば、摩擦・発汗・寒冷刺激などの非アレルギー性の要因によって生じるケースもあります。
アレルギー性の蕁麻疹は、症状が繰り返し現れることが多く、場合によっては呼吸困難などの重篤なアレルギー反応を引き起こすこともあるため、注意が必要です。特に、食品や薬剤が原因となっている場合は、原因の特定と回避が不可欠であり、外用薬だけでは改善が難しいこともあります。当院では、原因に応じた適切な治療をご提案しています。
アレルギー性鼻炎・結膜炎・花粉皮膚炎(花粉症など)
アレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎は、スギやヒノキの花粉、ダニ、動物の毛などに対するアレルギー反応によって起こる疾患です。これらのアレルゲンに反応すると、鼻水・くしゃみ・鼻づまり、目のかゆみや充血などの症状が現れます。一般的には「花粉症」として知られています。さらに、花粉が皮膚に付着して起こるアレルギー性の花粉皮膚炎も起こります。主に顔(特にまぶた・頬・首など露出部)に赤み・かゆみ・湿疹が出るのが特徴です。
症状の出方や重症度は、体質や生活環境によって異なり、特定の季節だけ症状が出る方もいれば、通年性アレルギーとして慢性的に悩まされる方もいます。当院では、各患者様の症状や生活背景に合わせて、最適な治療法や予防策をご提案しています。お困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
食物アレルギー
小さなお子様は、蕁麻疹がきっかけで食物アレルギーが見つかるケースが多く、発疹以外にも咳や喘鳴(ゼーゼーという呼吸音)、嘔吐、下痢などの症状を伴うことがあります。
また、学童期以降に多く見られる花粉症では、花粉に対するアレルギー反応と同時に、果物アレルギーを併発することがあります。これは「花粉-食物アレルギー症候群(PFAS)」と呼ばれ、花粉の飛散時期に限らず、季節を問わず果物を食べることで症状が出ることがあるため注意が必要です。
当院では、食物アレルギーのお子様に対して、症状の経過、血液検査の結果、日常の食習慣などを総合的に評価し、ご家族と連携しながら無理のない治療方針を検討・提案しています。
金属アレルギー
金属アレルギーは、金属が皮膚に触れることで発症するアレルギー性接触皮膚炎の一種です。汗や体液によって金属から溶け出したイオンが体内のタンパク質と結合し、それが異物と認識されて免疫が反応することで、かゆみや腫れなどのアレルギー症状を引き起こします。なかでも最も頻度が高いのが「ニッケル」によるアレルギーです。ニッケルは、アクセサリーや腕時計、ベルトのバックル、食器、携帯電話、さらには50円玉や100円玉などの硬貨にも使用されており、私たちの身の回りの様々なものに含まれています。
薬アレルギー(薬疹)
薬疹は、薬の成分に対する体の反応で皮膚に発疹が出る状態をいいます。あらゆる薬が原因になりますが、抗菌薬、解熱鎮痛薬、抗けいれん薬、循環器疾患治療薬、抗腫瘍薬の頻度が高いです。多くは薬を飲んで数日〜2週間後に赤い発疹やかゆみが現れます。軽いものはかゆみや紅斑のみですが、発熱や全身の水疱、皮膚が剥がれる重症型(Stevens-Johnson症候群や中毒性表皮壊死症)になることもあります。原因薬の中止が最も重要で、必要に応じて抗ヒスタミン薬やステロイド薬で治療します。
当院で行うアレルギー検査
view39
当院では、39種類のアレルゲンを一度の採血で調べられる血液検査「View39」を導入しています。アレルギーの原因が特定できない場合や、花粉と果物の交差反応が疑われる方、学童期以降のアトピー性皮膚炎の方において、原因となるアレルゲンの特定に有効です。
測定可能な39項目
吸入系・その他アレルゲン(19項目)
- ヤケヒョウヒダニ
- ハウスダスト1
- イヌ皮屑
- ネコ皮屑
- ゴキブリ
- ガ
- スギ
- ヒノキ
- シラカンバ属
- ハンノキ属
- カモガヤ
- ブタクサ
- ヨモギ
- オオアワガエリ
- アルテルナリア(ススカビ)
- アスペルギルス(コウジカビ)
- マラセチア属
- カンジダ
- ラテックス
食物系アレルゲン(20項目)
- オボムコイド
- 卵白
- ミルク
- 米
- 小麦
- 大豆
- ピーナッツ
- ゴマ
- ソバ
- エビ
- カニ
- キウイ
- バナナ
- リンゴ
- マグロ
- サバ
- サケ
- 牛肉
- 鶏肉
- 豚肉
アレルゲンの推定が難しいケースや複数のアレルギーが疑われる場合のスクリーニングとして有用です。検査をご希望の方は、どうぞお気軽にご相談ください。
金属パッチテスト
金属アレルギーの診断には、アレルギーの原因と考えられる金属成分を含む試薬を、皮膚に一定時間貼付し反応を確認する「金属パッチテスト」を行います。これは、金属によって皮膚がかぶれるかどうかを意図的に調べることで、どの金属がアレルゲンかを明らかにする検査です。
パッチは上背部または上腕に貼付しますので、衣服で隠れる部分に行う検査となり、見た目を気にされる方も安心して受けて頂けます。
金属アレルギー検査の検査項目
- 塩化アルミニウム
- 塩化第二スズ
- 塩化第二鉄
- 塩化コバルト
- 塩化パラジウム
- 塩化マンガン
- 三塩化インジウム
- 四塩化イリジウム
- 臭化銀
- 重クロム酸カリウム
- 硫酸ニッケル
- 塩化亜鉛
- ヘキサクロロ白金酸
- テトラクロロ金酸
- 硫酸銅
薬剤誘発性リンパ球刺激試験(DLST)
DLSTは、薬アレルギーの原因を調べるための血液検査です。薬に対して過剰反応するリンパ球があるかを、患者さんの血液に薬を加えて反応の強さを測定することで調べます。皮膚に薬を使わないため安全ですが、すべての薬アレルギーを正確に判定できるわけではなく、参考検査の位置づけです。検査をご希望の方は、どうぞお気軽にご相談ください。
舌下免疫療法(シダキュア、ミティキュア)
 舌下免疫療法は、アレルゲンに少しずつ体を慣らすことで、体質そのものを改善し、アレルギー症状の緩和を目指す治療法です。
舌下免疫療法は、アレルゲンに少しずつ体を慣らすことで、体質そのものを改善し、アレルギー症状の緩和を目指す治療法です。
アレルギーには、スギなどの花粉によって特定の季節に症状が現れる「季節性アレルギー」と、ダニやハウスダストなどによって一年中症状が続く「通年性アレルギー」があります。当院では、スギ花粉症やダニアレルギーに対して舌下免疫療法(アレルゲン免疫療法)を行っております。 スギ花粉やダニ抗原を原料としたアレルゲンエキスを含有した錠剤(シダキュア、ミティキュア)を舌の下に置き、1分間保持した後に飲み込みます。1日1回長期に服用することによって体を慣らし、アレルギー症状を和らげるだけでなく、根本的な体質改善を目的とした治療です。
ダニアレルギーの場合は年間を通していつでも治療を開始できます。スギ花粉症の場合は花粉の飛散時期を避けて治療を始める必要があります(6月~12月)。受験や就職、進学など春に重要なイベントを控えている方には、早めの開始が特にお勧めです。
効果が現れるまでには一定の期間がかかるため、アレルギー症状の改善を希望される方は、お早めにご相談ください。いずれも保険適応の治療になります。